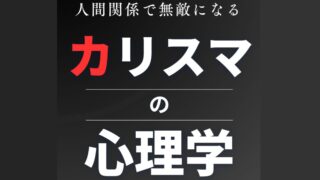ああもうまたやっちゃった!
自分がイヤになる…

さっきちょっとキツい言い方をしていたみたいだけど、大丈夫?

はい…自分でもわかってるんです。
でも余裕がなくて人に優しくできなくて…わかってるんですけど、私はイヤな人間だって思って気分悪くなっちゃうんです

余裕がない時は誰しもそう考えちゃうときがあるよね。
でも、あなたの考えで明らかに間違いな部分があるよ

…私がダメなのはわかってますよ

全くもってそこじゃない。0点だ。悪いのは自己嫌悪の部分だ。
じゃあ、今回は今の考えが良くない理由と、自分にも周りにも優しくなれるための心理学をエビデンスを元に解説してみよう!

おねがいします!
自分の行いを振り返ることができているだけで優勝している

まず一番重要なこととして、「やっちゃったな」「あれはマズかったな」と思える事は悪い事ではない。悪いどころか優勝一歩手前だ。
なぜかというと、自分のしたことを振り返り、悔いる人間は成長して変われるからだ

何を言っているんですか??
周りに冷たくしたり塩対応しちゃったら、後悔したり自己嫌悪するのは当たり前じゃないですか

全然当たり前ではない。
なめくさった態度を取ったり冷たい対応をする人の中には、自分がやっていることには何の問題もないと感じている無敵キャラがいる。
このような人は自分を振り返ることがないので自己嫌悪に陥ることがない。
その代わり、人生の落とし穴にもハマりやすいんだがな

たしかに、態度悪いのに全然悪びれることがない人いますもんね。
…じゃあ、自己嫌悪になる人と自分を振り返らない人、どっちの方が幸せなんでしょう?自己嫌悪にならないのは羨ましいですが…

私は自己嫌悪に陥らない人の方が圧倒的に苦しい人生になると思う。
自分の欠点を修正できないという時点で人生ベリーハードモードになる。
特に人生の後半戦は大変だぞ。いざ問題が発生してドツボにハマったとしても、その原因が自分であることに気づかないし、気づけない。
だから他責思考になり、最終的にはぼっちになる。誰からも助けてもらえない

じゃあ、この自己嫌悪は最悪な状況になることを防いでくれるってことですか?

そうとも言える。…が、自己嫌悪止まりだと成長の素養はあるんだが、惜しいんだ。そのせいで成長が遅くなり、必要以上に苦しんむ事になる。
だからまずは自己嫌悪をどう扱い、軽くするのかという方法について解説する。
その後、周囲に優しくするための具体的方法に入っていくぞ
まとめ
自己嫌悪は成長の一歩目!だけどちょっと惜しい状態
なぜ自己嫌悪が起きるのか?答えはレッテル貼り

そもそも、どうして自己嫌悪に陥ってしまったんだろう?
あなたは魔王で、地球でも滅亡させたんだろうか?

茶化すのもいい加減にしてくださいよ。
イライラしたり、冷たい態度をとった自分が最低な人間だと感じてしまっているんですよ。共感能力ないんですかあんたは

最後の一言は余計だが、そんなところだろうな。
良くない行いをしたがゆえに、自分が悪い人間だと感じてしまう。
だがこの考えはまったく妥当ではない

どこがおかしいんですか?

あなたが冷たい態度を取ったのは事実なんだろう。
だからといって最悪な人間ではないだろう。
もちろん悪意を持って世界を滅亡させたというのなら少しは納得できるが…

世界滅亡を持ち出すなんて、ちょっと極端すぎませんか?

そうだね。私の考えは極端だ。
そして、あなたの考えも同じように極端だということがわかるかな?
最も悪いというくらいだから、世界滅亡くらいしてもらわないと最高に悪いところまでは振り切れない。
誰かに冷たい態度を取ったくらいで悪い人間というのなら、全人類は悪い人間になってしまう

ですが、私が優しくない態度を取ったことは変わりません

そうだね。
あなたは優しくない態度をとった人ではある。これは正確な表現だ。
そして、それは普通の人だ。
時にイライラする事や、余裕のない時に冷たい態度をとったりしてしまうことは誰しもある。
さらに冷静になって考えてみれば、今まで優しい態度もたくさん取っているはずだ

このような普通の人に「最悪の人間」「イヤなやつ」というレッテルを貼ることは悪い影響しかない。
だって、もし「最悪の人間」なら自分の行動を振り返って後悔したり、ましてや成長のための対策なんてしないだろう?

そうですね。
つまり…自分に悪い人間とレッテルを貼る事は、何もしないための言い訳になるんですね!

そういうこと!
このレッテル貼りというのは認知の歪みでよく見られるものだ。
この考えでは自己嫌悪にはなるし、何もしなくなる。
だから自分に「悪い人間だ」と悪いレッテルを貼るのはやめよう。
そして自分を悪い人間ということにして努力をサボるな。

今の話はCBT(認知行動療法)の考えが含まれている。
参考文献でもあるいやな気分よ、さようならには認知の歪みの解説や、バーンズ博士が対話の中でレッテル貼りや極端な思考に気づかせる例が紹介されている。
このような思考になりやすい人はぜひ参考にしてみてくれ

わかりました!
私は良いことも悪いこともする普通の人間です。
そして、今より少しだけやさしい人になるために…その改善方法を聞いたろやないかい!!
まとめ
自分に悪いレッテルを貼って終わりにしない
人に優しくするメリットを知ると、親切が続けられる

では、自分がどうすれば優しい行動を増やせるのかを解説しよう。
人間の行動には、インセンティブ(ご褒美)が大きくからんでいる。
たとえば、私たちが仕事やアルバイトをするのはなぜだ?

もちろんお金のためです(国民の義務だからです)

本音とタテマエが逆になっているぞ。
だが正解だ。お金というご褒美(インセンティブ)がもらえるから仕事をする。
褒められたり、人から感謝されたりする事もご褒美になるが、これもインセンティブ※の一種だ
※インセンティブについての補足
経済学者であるスティーヴン・D・レヴィット教授はヤバい経済学にて、インセンティブには基本的に3つあり、経済的・社会的・道徳的インセンティブがあると述べています。4)
このインセンティブにより人間は行動をするし、さらに人間がインチキをするのもインセンティブがからんでいる…ということを解説した本です。
都合の良い話にだまされないために読んでおくといいかもしれません。

人間はなんかイイ事があるとその行動を続けるようになるってことですね!

その通りだ。
じゃあ、優しく利他的な行動をするたびにご褒美があるとしたらどうだ?

ご褒美があるなら当然、もっと親切をしようと思うはずです!
…でも他人に優しくするだけでいいことがあるなんて、そんなスピリチュアルなことがあるわけ…

ある。
私のことだから当然スピリチュアルではない。
2018年Curryらの助けることと幸福に関するメタ分析によると以下のことが述べられています。
- やはり他者に親切をすると幸福感を向上させるようだ!
- 親切の効果は他のポジティブ心理介入(マインドフルネス、ポジティブシンキング、ラッキーな事を数えるなど)と同程度だった
- これらは短期的な結果であり、長期的な幸福に効果があるかは調査が必要だが、利他的行動には地位を向上させたり恋愛パートナーを見つける機能もあるから、今後はそこを測定すればわかるかも?1)

ん?「親切をした人が」ハッピーになるってことですか?

そうだ。
情けは人のためならずと言うが、実は親切をする側の人間の幸福度が高まるんだ。
さっきも言ったようにご褒美があればクセになって人は親切を続けるだろう。
この論文でも利他的な行動は友達作りや地位を向上させたり、パートナー探しに役立つことについて述べられている。
利他的な行動により状況が好転していく事は十分にありうる話だと私も思うぞ

すぐハッピーになれて、しかも長期的にもメリットがあるかもしれないとなれば
これは今日からでも親切したほうがいいですな!
まとめ
親切にすると自分にもメリットがある!
マインドフルネスでより親切に!という研究

さらに、マインドフルネスによっても利他的行動が促されることがわかっている
2017年Donaldらのマインドフルネスと向社会的行動について調べたメタ分析によると、
- マインドフルネス(介入・性格特性双方)は社会性のある行動と有意に関連していた!
- その理由は、マインドフルネスは共感や感情コントロールがうまくなり、社会性を高めるからかも?2)

マインドフルネス瞑想の経験とエビデンスについて、過去記事で5年のマインドフルネス介入経験談を書いてましたよね。
その時は利他的になりました?

すまん、私は元々利他的な行動が多いからよくわからんのだ。
なにしろ利他的行動のメリットをデータとして知っているからな。
だが共感や感情調整については鋭くなったことは自覚があった。
人の気持ちを察する能力が磨かれたから、芯の食った親切ができていたように思うぞ

親切にも良し悪しがあるんですね

おせっかいにならないレベルでの手助けがいいんだ。
そのためには相手の感情や考えを推測する必要がある。
その点、マインドフルネス瞑想は良かったと思うぞ

共感性が高まるからかも?と言ってましたもんね。
ところで、前項の研究では利他的行為とマインドフルネス瞑想は同じくらい幸福度に影響していたんでしたよね。
じゃあ両方やれば2倍ハッピーに…

そんな単純な話なわけないだろ。
マインドフルネス→利他的行動→ハッピーだとすれば、単に利他的行動が増えたからハッピーになっているだけの可能性がある。少なくとも全く別物ではない。
とはいえ、感情調整や共感能力が高まることだけでも、幸福度は高まるかもしれん。
二倍ハッピーという考えは安易だが、重ねがけすることで幸福度は高まりやすいかもしれないな

よっしゃあ!マインドフルネスと親切でハッピーになるぞ!!
…ところで、親切って何からすればいいんですか?

たしかに、具体的な親切の方針がある方が親切をしやすいよな。
じゃあスベらない親切のコツについて解説しよう
まとめ
マインドフルネスで利他的になるぞ!
心理学を使ったスベらずに優しくするコツは「相手の状況になって実況中継」

さっきも言ったが、親切というのはおせっかいになることもある。
だから相手の感情や考えを推測することが重要だ。
よって、ジャーナリングが有効だ

ジャーナリングってコールドリーディングの練習法で使ったやつですよね?
確かあれは占い師が好んで使うテクニックで、相手の心を読んだように見せかけるものだったはず…

そうだ。
コールドリーディングの基本的な考えとして、人間同じ状況なら同じようなことを考えるというものがあるんだ。5)
たとえば、朝職場の自分のデスクに来たら何をする?パソコンの電源を入れるか、今日の予定を確認して仕事の準備をするんじゃないかな?

当たり前じゃないですか

じゃあ、朝デスクの前でいきなり踊り始めたり、隣の人に脱いだ靴下を投げることはあるかな?

あるわけないじゃないですか

そういうことだ。
人間同じ状況なら、みんな似たような考えや行動をとる。
そのパターンは何パターンかあるだろうが、どれに当てはまるのか考えればいい。
そのパターンを読むにはジャーナリングが一番だ

具体的にはどうすればいいですか?

たとえば、仕事で大きなミスをして落ち込んでいる人がいたとする。
その時自分ならどう思うだろう?
「他の人に迷惑をかけてしまった、みんな自分のことをダメなやつだと思ったに違いない。自分はダメなやつだ」とかかな

わかります!その気持ちめっちゃわかります!

じゃあ、そんな時自分なら何をされると嬉しいだろう?
①自分がやった過去の大きなミスを話すことで、ミスは誰しもあることで、なんとかなっているという事実を見せる
②缶コーヒーを渡して励まし、いまはそっとしておく
こんな事をされると「嬉しいな、仲間がいて良かったな」と私なら思う

どちらもグッときます!
もし相手が話をしたそうな状況なら②を、あまり話せる状況でなければ①を選んだらいいかもしれません

そうだね。相手の事を考えたいい選択だね。
相手の立場になりきって何を考えているか・どう感じているかを実況中継するんだ。
そして、その立場だったら何をされると嬉しいか。
これに慣れてくると親切のスペシャリストになれる。
つまりあなたが親切でハッピーなヤツになるってわけよ

よーし、私もハッピーになるぞ!

もっと詳しい解説はコールドリーディングの過去記事があるからそちらを参照してくれ。
これはやればやるほど相手の気持ちや考えがわかるようになるし、親切も芯を食ったものになる。
あなたの力で自分も周りの人もみんなハッピーにしちゃおう!
※補足
コールドリーディングのジャーナリングに関しては、邦書だとなかなか解説書が見当たりません。
英語になりますが今回の参考文献、George HuttonのCold Reading(タイトル訳:コールドリーディング:相手の考えを知り、心を読み、未来を予測する)は良書です。比較的かんたんな英語ですので、コールドリーディングに興味がある方はトライしてみてください。
引用・参考文献
1)Curry, Oliver Scott, et al. “Happy to help? A systematic review and meta-analysis of the effects of performing acts of kindness on the well-being of the actor.” Journal of Experimental Social Psychology 76 (2018): 320-329.
2)Donald, James N., et al. “Does your mindfulness benefit others? A systematic review and meta‐analysis of the link between mindfulness and prosocial behaviour.” British Journal of Psychology 110.1 (2019): 101-125.
3)いやな気分よ、さようならコンパクト版: 自分で学ぶ「抑うつ」克服法. 日本, 星和書店, 2013.
4)レヴィット, スティーヴン・D., and ダブナー, スティーヴン・J.. ヤバい経済学: 悪ガキ教授が世の裏側を探検する. 日本, 東洋経済新報社, 2006.
5)Cold Reading: Know Their Thoughts – Read Their Mind – Predict Their Future (English Edition),George Hutton